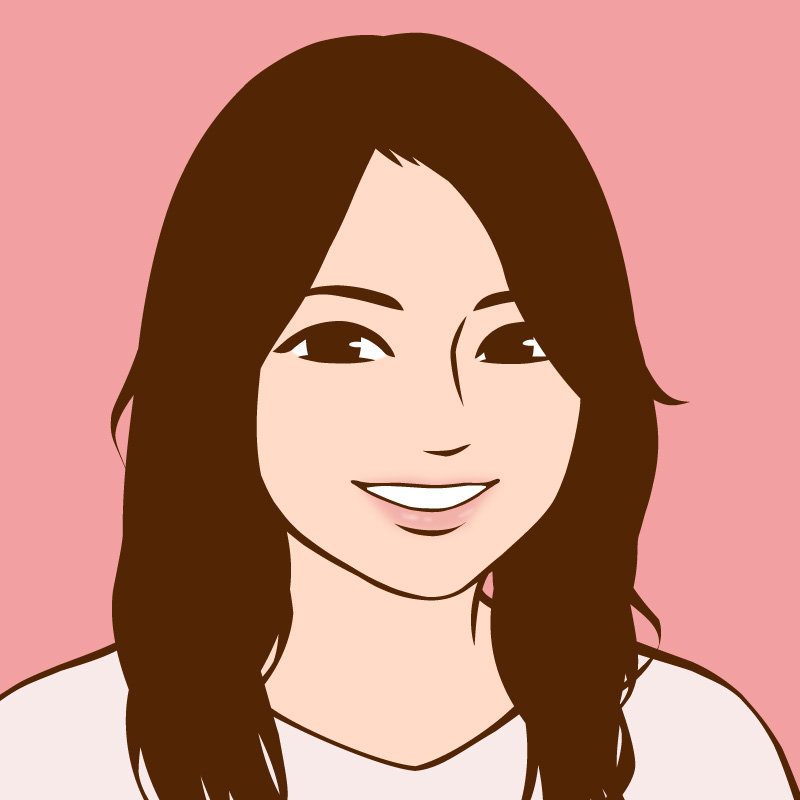こんにちは!『決算分析目安辞典』運営者のレイです。
このブログでは経営や企業戦略に興味がある人が、楽しみながら会計を学べることを目指しています!
運営者の基本情報
- 名前:レイ
- 性別:女性
- 年齢:27歳(1994年生)
- 出身:大阪府
- 経歴:京都大学→長期インターン(広報)→経営コンサル
メーカー・商社・金融・航空などのプロジェクトに参加 - 会計システムの導入プロジェクトを約2年経験
- 資格:簿記3級・2級(簿記1級勉強中)
なぜ会計を学ぶのか
会計を学ぶことは、投資・公認会計士・経理職以外でも、経営を知るうえで様々なメリットがあります。
- 決算書を通じて会社の業績や安全性、収益性が分かる
- 予算編成・決算・業績測定といった企業経営の根本を理解できる
- 決算書から社会の仕組み・ビジネスモデルを知ることができる
このように、会計学は経営と切っても切り離せない重要な知識です。
将来起業を考えている方、就職活動を控える学生、将来経営管理職への昇進を目指している方は一度は会計が重要であると聞いたことがありつつ、中々興味が出ないのではないでしょうか。
私は大学の卒業直前につぶしがききそうな簿記3級を取得したものの、同僚の経営コンサルタントの大部分と同じように、会計は難しくてつまらないものだと思っていました。
しかしバックグラウンドと関係なく会計システム導入プロジェクトのメンバーになったのをきっかけに、簿記2級を取得しました。
簿記をとったらついでに決算書が読めるようになることも期待していたのですが、いざ簿記2級に合格しても財務諸表と実際のビジネスと結びつけることは難しく、会計の知識が使えていないことにモヤモヤしていました。
会計を勉強しているうちに、企業は利益を目的の1つとしており、「コンサル・起業・経営に興味がある=会計にも興味がある」というのが自然ではないかと考え始めました。
(実際に、コンサルティングファーム最大手マッキンゼー&カンパニーの創始者「ジェームズ・マッキンゼー」はシカゴ大学の会計学教授だった)
ひっかかりを抱えながらしばらくたつと、財務諸表とビジネスを結びつけるには簿記の知識に加えて、決算書を読む練習が必要だということに気づきました。
ここでいう「決算書を読む」とは、投資家からイメージされるような難しい公式や数字を駆使する分析ではなく、身近なビジネスと会計を結びつけ、社会の仕組みを知ることです。
決算書に慣れてくると面白い事実がたくさん発見でき、それを友達に話すと会計と無縁の友達でも意外と興味を持ってくれることに気づきました。
確かに会計に関する書類は文字が多く読みにくいですが、決算書に書いてある事実がきちんと伝われば会計アレルギーを発症しなくなる人も多くいるはずです。
- 経営に興味があるけど会計に苦手意識を持つ人
- 決算分析を始めたけど挫折してしまった人
- 社会の仕組みを知りたい人
このような方に向けて、決算と関連している面白い事象や、決算分析を始めた頃にほしかった情報をブログに残すことにしました。
なんとなく会計を敬遠していたり、勉強のモチベーションが湧かない人も、経営と会計のどちらも学べる記事を目指していきます。経営に無縁でも読みやすい内容なので、気楽に読んでもらえると嬉しいです!
業界目安の完全版について
このブログの多くを占めている「業界目安の完全版」シリーズは決算分析を始めた時に本当に役立つ「業界ごとの指標の目安」を公開することが目的です。
私は経営状態を知るために何度も決算分析に挑戦しましたが、いつも挫折していました。うまくいかない要因の一つは、指標を公式通りに計算できてもよい経営をしているかの判断が難しかったからです。
経営状態がよいとされる数値は結局のところ、指標ごと・業界ごとに違います。指標の意味を理解し、ツールの知識がない中で計算するだけでも大変なのに、目安となる基準値まで調べる時間を確保するのはとても難しいです。
また、指標の目安をインターネットで調べても全業種共通で使われるざっくりとした目安や、主要なの業種の平均しかでてきません。
業界ごとの違いや大企業であることによる平均値からの差異は想像以上に大きいです。
例えば、流動比率は100%以上だと良好と言われていますが、東京電力は44%・関西電力は57%で、事業の特性上100%を大きく下回っている状態が通常運転の業界もあります。
>>>参考:「流動比率」業界目安の完全版
大企業だからといって経営状態がいいと言われる数値に近づくとは限らず、中小企業の平均値が大企業の平均値を上回ることも頻繁にあります。こうした中で、決算分析に興味があっても読めるようにならない人が多いのではないでしょうか。
また、近年は国際会計基準の普及により、国際基準を採用している企業と日本基準の企業で財務諸表の項目にばらつきがあり、ツールで機械的に抽出しにくい指標も多くなってきました。
このような問題を解決するため、記事の中身ではテーマとなる1つの指標について証券取引所で決められている金融を除く全29業種の売上上位3社の指標を1ページにまとめました。
金融業は決算項目が特殊なため指標の計算ができませんが、指標が計算できるものについては全業種網羅しているので決算分析の参考にしてみてください。
さらに、業界ごとの中央値・代表的な企業3社を売上の大きいに比較したグラフをスクロールしながら眺めることで売上と指標の値は連動するのか?業種によってどれくらい違うのか?などを知ることもできます。辞書的な使い方もできるので、ぜひ興味のあるところから見てみてください。
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございます!これから読者のみなさんが経営・会計を楽しめるような内容をどんどん発信していくので、ブックマークしてまた来ていただけるととても嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!